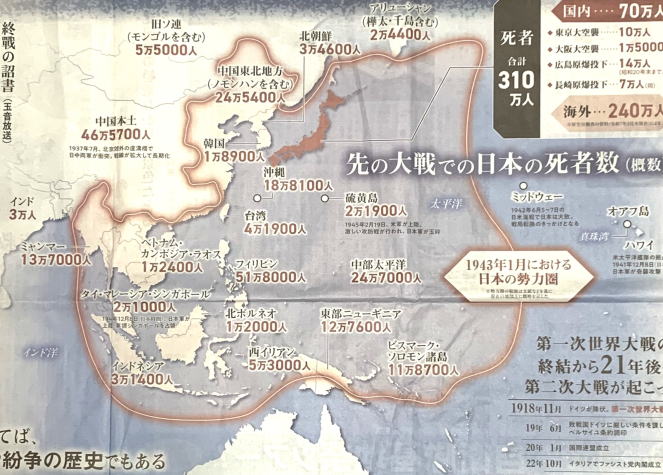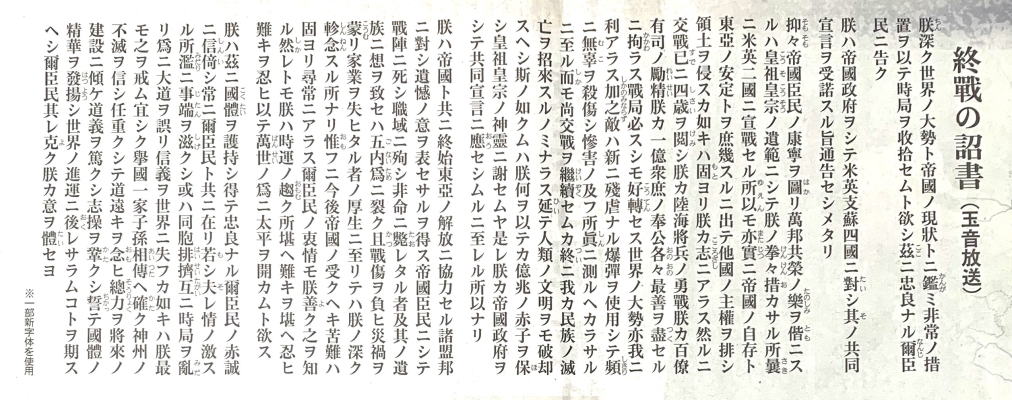 |
| 現代語訳 私は世界の情勢とわが国の現状を深く考え合わせ、非常の手立てをもって事態を収捨したいと願い、 ここに忠義厚く善良な国民たちに告げる。 " 私は米国、英国、中国、ソ連の4ヵ国に対し、その共同宣言を受諾する旨を政府に通告させた。 そもそも、国民が平穏無事に生活を送り、世界の国々とともに栄えるようにすることは、歴代の天皇が 残してきた手本であり、私の念願でもあった。米英 2ヵ国に宣戦布告した理由もまた、わが国の自存とア ジアの安定を心から望み願ったからであって、他国の主権を排し、領土を侵害するといったようなことは、 もとより私の意志ではない。しかし、戦争が始まり、すでに 4年の歳月が過ぎた。わが陸海軍の将兵たち は勇敢に戦い、役人たちも職務に励み、 1億の民たちも奉公し、それぞれが最善を尽くしてきた。それに もかかわらず、戦局は必ずしも好転せず、世界の情勢もまた私たちに有利とはいえない。加えて、敵は 新たに残虐な爆弾を使用して、罪なき民を殺傷した。痛ましい被害がどこまで広がるのか、その範囲は はかり知れない。交戦を継続すれば、最後はわが民族の滅亡を招くのみならず、ひいては、人類の文明 も破壊されることになろう。そうなれば、私は何をもって、大切なわが国の民たちを守り、歴代天皇の神霊 にお詫びすることができょうか。これが、私が共同宣言に応じるように政府に命じた理由である。 私はわが国とともに終始、アジアの解放に協力してきた友好諸国に対し、遺憾の意を表せずにはいられ ない。国民の中で、戦陣に死し、職域に殉じ、不幸な運命のもとに倒れた人々やその遺族たちに思いをい たせば、本当に悲しみに堪えない。また、戦傷を負い、災禍を被り、家業を失った人々の生活の厚生は、 私が深く心を痛めるところである。今後、わが国が受けるべき苦難は並大抵のものではないだろう。国民 の心中はよく分かる。しかし、私は時世の巡り合わせの赴くべきところ、堪え難きを堪え、忍び難きを忍び、 この先も長く続く未来のために平和を実現したいと思う。 私はここに国体を護持することができ、忠義に厚い国民たちの誠実な心を信頼し、常にあなたたち国民 とともにある。もし感情の激するままに争ったり、同胞同士が互いに相手を陥れたりして、道を誤り、その ために世界からの信頼を失ってしまうようなことがあれば、それは私の最も戒めるところだ。どうか、一丸 となってこの国を子孫に伝え、神州の不滅を信じてほしい。国の再建と繁栄への責務は重く、道のりは遠 いことをよく理解して、将来の建設に力を傾けてほしい。道義を大事にし、志を固くして、わが国の美点を 発揮し、世界の進歩に後れを取らないように肝に銘じなければならない。国民よ、あなたたちが私の心を 理解し、行動することを願う。 (監修・川上和久麗澤大教授) |